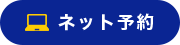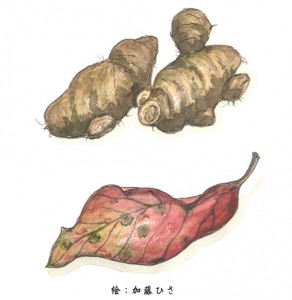第2回 歯の「なおしびと」と「つくりびと」
歯顎塾
歯の噛みあわせは、歯の「なおしびと」と「つくりびと」の噛みあわせです。
自分の歯が大切なら、あなたの身体の一部になる人工の歯も同じく大切です。
きちんとつくられた人工の歯が口の中の健康を支えてくれる、それは誰にとっても大変ありがたいことですよね。
だから、歯をなおしてくれる人と歯をつくってくれる人がもしも同じなら、患者にとって一番わかりやすく、それが理想だと思うのは私一人でしょうか。
今から50年近く前、まだ私が子どもだったころ、通っていた歯医者さんが、まさにそうでした。その当時はどの歯医者さんも程度の差はあれ、 自分で自分の患者の歯科技工をしていましたし、私の歯科医師国家試験のときには、筆記試験のほかに技工の実技試験がまだまだ健在でした。
製造者責任ということば通り、患者の歯の健康について主治医である歯科医師が技工を担うのは大変意味のあることではないでしょうか。たとえ一部であったと しても歯科医師が細かな技工を手掛けると、噛みあわせ治療のレベルも上がることにつながるのです。新たに歯の噛みあわせをつくる一般臨床の成否は、歯の噛 みあわせをつくる技工テクニックがあってのこと。
それらはともに直結していることから、歯科医師自らが「噛みあわせは技工がカギ」と位置づけているのも、当然なことと思います。
もちろん歯を新しくつくらない噛みあわせの臨床においても、技工で培ってきた技能が、噛みあわせの調整テクニックの精度向上に反映することは、歯科医師なら誰でも知っています。
「歯をなおすことになったが」「歯を入れることになったが」その歯は誰がつくっているの?現代は何かにつけて分業の時代。歯科の場合も 同じで、歯をなおす人と歯をつくる人が別々というのが当たり前になってきています。しかし、あなたの歯をつくるのが、あなたの主治医自身であると、
- 1、つくる人が分かっていて、安心
⇒(製造者が明確) - 2、つくる人が、あなたの歯医者なら、さらに安心
⇒(つくった本人だから、その歯に愛着がある) - 3、その歯に何かあったら、やっぱり一番安心
⇒(こまめなメンテナンス、そして必要に応じた修正が可能)
やむをえず、人工の歯を入れることになったが、どんなものがあって、
- かかる費用は?
- できる日数は?
- 使える期間は?
- それだけでなく、自分の歯となってくれる、その人工の歯はだれがつくってくれる?
- 後にどんなトラブルが考えられて、どんなリスクがある?
歯のなおしびとが、歯のつくりびとなら、あなたと「もっと歯の考えびと」になれます。